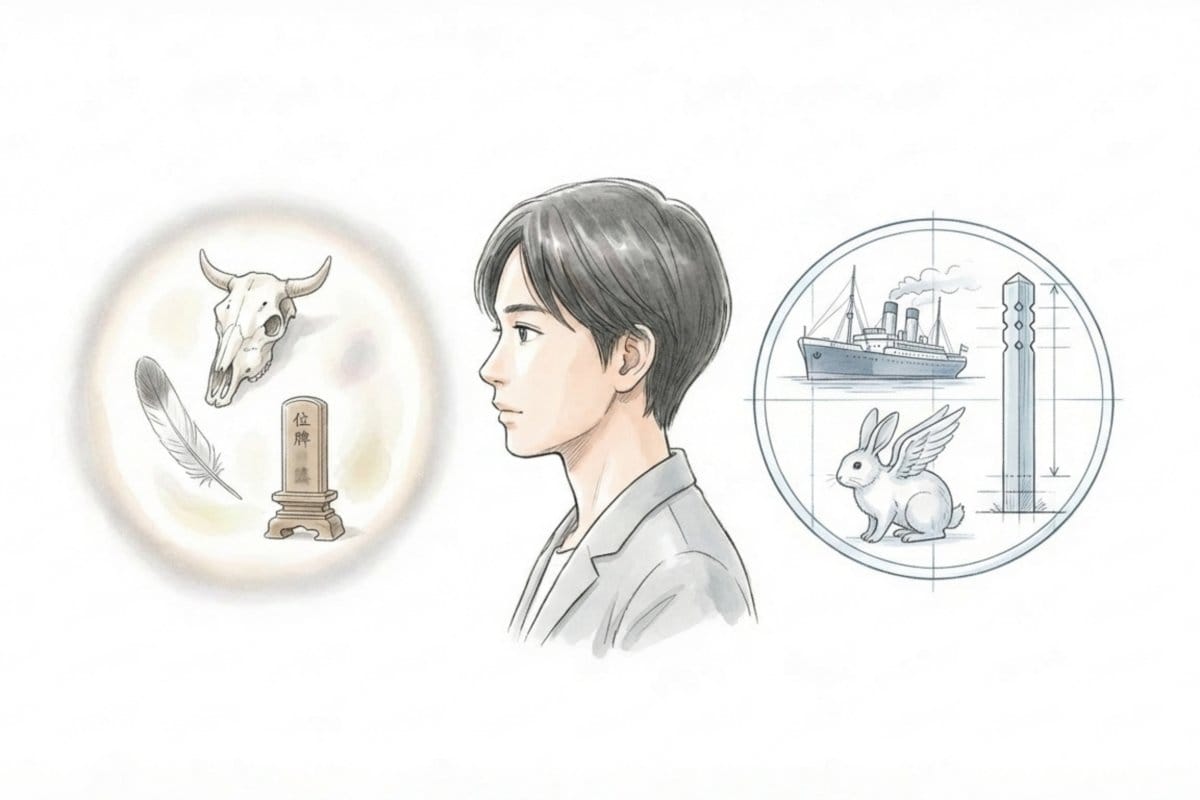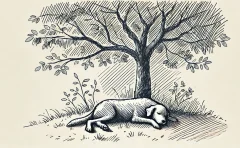「動物にも血液型はある?」と疑問に思ったことはありませんか。
人間と同じように、実は多くの動物にも血液型が存在します。
例えば、身近な犬や馬の血液型は、私たちのABO式とは全く異なる分類がされています。
この記事では、そうした様々な動物の血液型について、分かりやすい一覧を交えながら詳しく解説します。
ゴリラは本当にB型しかいないのか、動物で多い血液型はO型なのか、といった興味深いトピックから、血液型と性格の関連性、さらにはウサギの血液型は?あるいはカエルの血液型は?といった少しマニアックな疑問まで、幅広く掘り下げていきます。
また、AB型しかいない動物がいるのかという点にも触れていきますので、ぜひ最後までご覧ください。
- 犬や猫、馬など主要な動物の血液型の種類と分類方法
- ゴリラのように特定の血液型しか持たない動物の事例
- 輸血の際に重要となる血液型の適合性と注意点
- 動物の血液型に関する興味深い豆知識や雑学
様々な動物の血液型とその分類

- 動物にも血液型はある?
- 犬の血液型であるDEA式とは
- 馬の血液型は3兆通り以上ある
- 動物で特に多い血液型はO型か
- ゴリラは本当にB型しかいないのか
- 血液型と性格の関連性について
動物にも血液型はある?

はい、人間と同じように多くの動物にも血液型が存在します。
血液型とは、赤血球の表面にある「抗原」というタンパク質などの物質の種類によって決まる、血液の分類のことです。
この基本的な仕組みは、動物でも人間でも変わりありません。
ただし、その分類方法は動物の種類ごとに大きく異なります。
人間の場合、「ABO式」や「Rh式」が広く知られていますが、動物たちはそれぞれ独自の血液型システムを持っています。
そのため、人間のA型やB型といった分類が、そのまま他の動物に当てはまるわけではありません。
なぜなら、種によって赤血球の表面にある抗原の種類が全く異なるからです。
この抗原の違いは、万が一の輸血の際に非常に大切になります。
適合しない血液を輸血すると、体内で免疫系が「異物」と判断して攻撃を始め、深刻な拒絶反応を引き起こす可能性があります。
したがって、動物医療においても、輸血前には血液型を特定することが不可欠です。
犬の血液型であるDEA式とは

犬の血液型は、現在国際的な基準として「DEA式」が用いられています。
DEAとは「Dog Erythrocyte Antigen」の略で、「犬赤血球抗原」を意味します。
現在、DEA1、DEA3、DEA4、DEA5、DEA7など、13種類以上の血液型が報告されていますが、輸血の際に最も重要視されるのが「DEA1.1」です。
このDEA1.1を持っているか持っていないかで、犬は「DEA1.1(+)」と「DEA1.1(-)」に大別されます。
日本の犬の約7割から8割がDEA1.1(+)とされています。
犬の輸血における大きな特徴は、生まれつき他の血液型に対する抗体(自然抗体)を持っていない点です。
このため、DEA1.1(-)の犬に初めてDEA1.1(+)の血液を輸血しても、急激な拒絶反応は起こりにくいと考えられています。
しかし、注意が必要なのは2回目以降の輸血です。
一度目の輸血で体内に抗体が作られてしまうため、2回目に再び不適合な血液を輸血すると、急性溶血反応という、赤血球が破壊される危険な拒絶反応を起こすリスクが高まります。
これらの理由から、犬に輸血を行う際は、事前に血液型検査と、輸血する血液との適合性を調べる「クロスマッチテスト」の実施が推奨されます。
馬の血液型は3兆通り以上ある

馬の血液型は、知られている動物の中でも特に複雑です。
現在、馬の血液型を決定する抗原システムは「A・C・D・K・P・Q・T」など8種類が確認されています。
そして、これらの抗原の組み合わせによって、理論上は3兆通り以上という天文学的な数の血液型が存在すると考えられています。
これだけ種類が多いと、完全に一致する血液を見つけることは極めて困難です。
しかし、馬は犬と同様に、生まれつき他の血液型に対する強い自然抗体を持っていないという特徴があります。
このため、血液型が完全に一致していなくても、他の動物に比べて輸血による拒絶反応のリスクが比較的低いとされています。
それでも、リスクをゼロにするために、馬の輸血では「ユニバーサルドナー」と呼ばれる、どの馬にも比較的安全に輸血できる血液を持つ馬の血液が用いられることがあります。
特にハフリンガー種などは、拒絶反応を起こしにくい血液を持つ個体が多いとされ、ユニバーサルドナーとして活躍する場合があります。
動物で特に多い血液型はO型か

「動物で多い血液型はO型」という話を耳にすることがありますが、これは一概に正しいとは言えません。
血液型の分布は動物の種類によって大きく異なり、特定の血液型が優勢な種もあれば、多様な血液型を持つ種も存在します。
例えば、人間に最も近いとされるチンパンジーでは、A型とO型が多く、B型やAB型はほとんど確認されていません。
この点は、人間に近い傾向と言えるかもしれません。
一方で、私たちの身近なペットである猫の場合、日本にいる個体の約95%がA型とされており、B型やAB型は少数派です。
また、豚はA型が9割以上を占めていることが知られています。
このように、種によって優勢な血液型は全く異なります。
| 動物の種類 | 優勢な血液型(日本国内のデータ等) |
|---|---|
| 猫(日本猫) | A型が約95%を占める |
| 豚 | A型が90%以上を占める |
| チンパンジー | A型とO型が多い |
以上のことから、「動物ではO型が多い」と断定することはできず、実際には種ごとに血液型の分布パターンが大きく異なるのが実情です。
ゴリラは本当にB型しかいないのか

ゴリラ、特にニシローランドゴリラは、ほぼ全ての個体がB型の血液型を持つことが確認されています。
これは、動物界全体を見ても非常に珍しい事例です。
他の多くの動物種では複数の血液型が共存しているのが一般的ですが、ゴリラのように一つの血液型にほぼ統一されている種は稀有な存在と言えます。
なぜゴリラの血液型がB型に統一されたのか、その正確な理由はまだ完全には解明されていません。
進化の過程で、B型の血液型がゴリラの生息環境や特定の病気への耐性などにおいて、何らかの生存上の利点を持っていた可能性が指摘されています。
この事実は、血液型の進化を考える上で非常に興味深い研究対象となっています。
他の類人猿であるチンパンジーがA型とO型を主に持つのとは対照的で、近縁種であっても血液型の分布が大きく異なることを示す好例です。
血液型と性格の関連性について

人間においては「A型は几帳面」「B型はマイペース」といった血液型による性格診断が広く知られていますが、動物の血液型と性格の間に科学的な関連性があるという証拠は現在のところ存在しません。
これは人間の場合と同様で、性格は遺伝的要因、育った環境、社会的な関係など、多くの要素が複雑に絡み合って形成されるものと考えられています。
例えば、日本の猫の約95%はA型ですが、全てのA型の猫が同じ性格というわけではないことは、猫を飼っている方なら実感できるでしょう。
「B型の猫は警戒心が強い」といった話が聞かれることもありますが、これはあくまで統計的な傾向や一部の観察に基づくものであり、科学的に証明された事実ではありません。
前述の通り、ゴリラはほぼ全てがB型ですが、彼らの社会性や行動は、種としての生態や群れの中での学習によって形成されるものであり、血液型が直接性格を決定づけるものではないのです。
動物の行動や性格を理解する上では、血液型という単一の要因に注目するのではなく、その動物種全体の生態や個体ごとの特性を多角的に見ることが大切です。
動物の血液型に関する豆知識一覧

- ウサギの血液型は何種類ある?
- カエルの血液型は解明されている?
- AB型しかいない動物は存在するのか
- 輸血時に重要な自然抗体とは
- 様々な動物の血液型を知る意義
ウサギの血液型は何種類ある?

ウサギにも血液型は存在しますが、犬や猫ほど詳細な分類は確立されていません。
研究によれば、ウサギの血液型は主にA型とB型に分けられることが知られています。
輸血の機会が犬や猫に比べて少ないため、研究自体が限られており、分類システムも標準化されているとは言えないのが現状です。
ペットとして飼育されるウサギが増えるにつれて、怪我や病気による手術で輸血が必要になるケースも出てきています。
そのため、動物医療の現場では、ウサギの血液型に関するさらなる研究の進展が期待されています。
現状では、輸血が必要になった際には、犬や猫と同様に、事前に供血するウサギと受血するウサギの血液を混ぜ合わせ、拒絶反応が起きないかを確認する「クロスマッチテスト」を行うことが一般的です。
カエルの血液型は解明されている?

カエルを含む両生類や爬虫類の血液型については、哺乳類ほど研究が進んでおらず、まだ解明されていない部分が多く残されています。
これらの動物は、一般的なペットや家畜と比べて輸血を必要とする機会が極端に少ないため、医療的な観点からの研究の優先度が低くなりがちです。
ただし、一部の研究や情報では、カメやワニの血液型はB型のみである、といった報告も見られます。
しかし、これらの情報は断片的であり、全ての種に当てはまるわけではありません。
生態学や遺伝学の分野では、種の進化の系統を探る目的で血液型の研究が行われることがあります。
今後の研究によって、これまで謎に包まれてきた両生類や爬虫類の血液型の多様性が明らかになるかもしれません。
AB型しかいない動物は存在するのか

現在のところ、「AB型」の血液型しか持たない動物種は確認されていません。
AB型という血液型は、猫などで見られますが、非常に珍しい存在です。
例えば猫の場合、A型が圧倒的多数を占め、B型は少数派、そしてAB型は極めて稀な血液型とされています。
これは、A型の遺伝子とB型の遺伝子の両方を持って初めてAB型が発現するため、遺伝的にその確率が低くなるからです。
前述の通り、ゴリラがB型にほぼ統一されている例はありますが、これは単一の抗原タイプが優勢になった結果です。
AB型は二つの異なる抗原を同時に持つ状態を指すため、種全体がAB型のみになるという状況は、遺伝学的に考えて非常に起こりにくいと言えます。
したがって、「AB型しかいない動物はいますか?」という問いに対する答えは、「現時点ではいない」となります。
輸血時に重要な自然抗体とは

「自然抗体」とは、生まれつき自分の血液型にはない抗原に対して持っている抗体のことです。
この自然抗体の有無が、輸血の安全性を大きく左右します。
動物によって、自然抗体を持つ種と持たない種がいます。
| 自然抗体を持つ動物 | 自然抗体を持たない動物 | |
|---|---|---|
| 代表例 | 猫、牛 | 犬、馬 |
| 特徴 | 自分の血液型と異なる血液が体内に入ると、即座に強い拒絶反応(急性溶血反応)を起こす。 | 初めての輸血では、異なる血液型でも急激な拒絶反応は起こりにくい。 |
| 輸血時の注意 | 1回目の輸血から厳密な血液型適合検査(クロスマッチテスト)が必須。 | 2回目以降の輸血では抗体が作られているため、適合検査が必須となる。 |
自然抗体を持つ猫の輸血
猫は自然抗体を持つ代表的な動物です。
特にB型の猫は、A型の血液に対する非常に強力な抗体を持っています。
もしB型の猫にA型の血液を輸血してしまうと、輸血された赤血球が即座に破壊され、命に関わる深刻な副作用を引き起こす危険性が極めて高くなります。
このため、猫の輸血は必ず事前に血液型を特定し、適合性を確認することが絶対条件です。
自然抗体を持たない犬の輸血
一方、犬は自然抗体を持たないため、初回の輸血では比較的安全性が高いとされています。
しかし、一度輸血を経験すると、体内で抗体が産生されます。
そのため、2回目以降に不適合な血液を輸血すると、猫と同様に危険な拒絶反応を起こす可能性があります。
このように、自然抗体の有無によって、輸血におけるリスク管理の方法が大きく異なるのです。
様々な動物の血液型を知る意義

この記事で解説してきた様々な動物の血液型について、最後に重要なポイントをまとめます。
- 動物にも人間と同じく赤血球の抗原による血液型が存在する
- 動物の血液型は種ごとに分類方法が大きく異なる
- 犬の血液型は「DEA式」で分類されDEA1.1が特に重要
- 猫の血液型は「AB式」でA型・B型・AB型の3種類
- 馬の血液型は組み合わせが非常に多く3兆通り以上とも言われる
- ゴリラはB型にほぼ統一されている珍しい動物
- チンパンジーは人間と似てA型やO型が多い
- 日本の猫のほとんどはA型でB型やAB型は少数
- 豚はA型が大多数を占める
- 動物の血液型と性格の間に科学的な関連性は認められていない
- 輸血の安全性は「自然抗体」の有無に大きく左右される
- 猫は自然抗体を持つため初回から厳密な血液型適合検査が必要
- 犬は自然抗体を持たないため2回目以降の輸血で注意が必要
- ウサギにはA型やB型があるが研究は発展途上
- カエルなど両生類の血液型は未解明な部分が多い
- AB型しかいない動物種は現在のところ確認されていない
- 動物の血液型を知ることはペットの健康管理と救命医療に不可欠